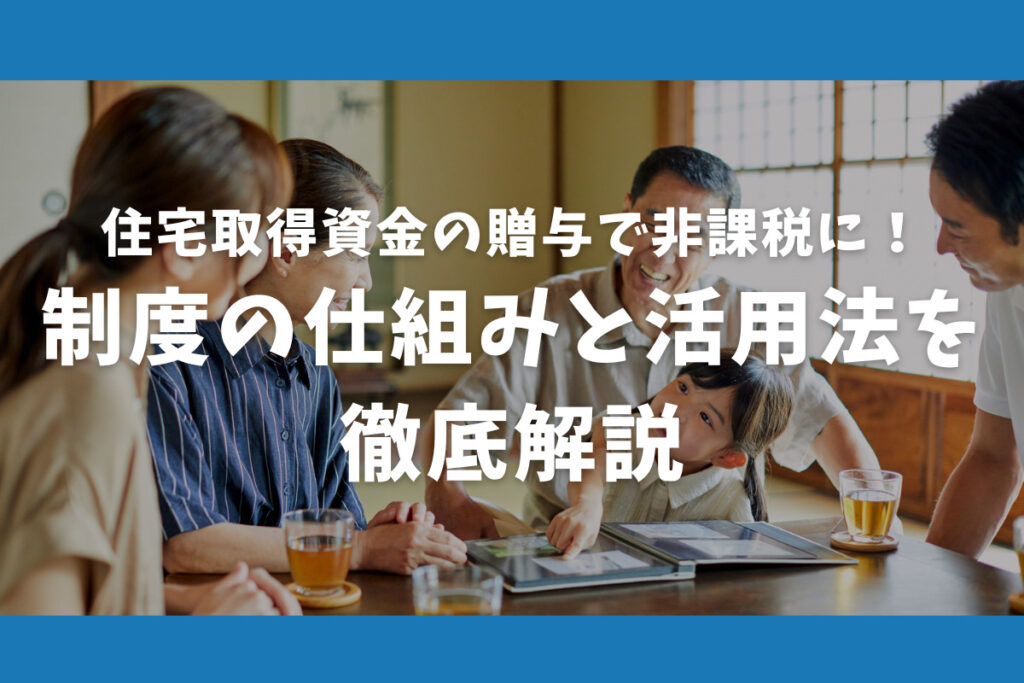はじめに:贈与を受けて家を買う方へ
「親から贈与を受けて家を買いたいけど、贈与税ってどうなるの?」
「非課税制度があるって聞いたけど、うちも対象になるの?」
住宅購入を考えている方のなかで、親からの援助や贈与を活用しようとするケースは少なくありません。ですが、「贈与税」という言葉が頭をよぎった瞬間、手が止まる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、2025年の税制改正を踏まえて、「住宅取得資金の贈与」に関する最新情報を、住宅購入初心者にもわかりやすくお伝えします。
1. 住宅取得資金の贈与とは?
「住宅取得資金の贈与」とは、親や祖父母などの直系尊属から、住宅の購入費用のためにお金をもらうことです。このお金は、通常なら「贈与税」の対象ですが、条件を満たすことで一定額まで非課税にすることができます。
2. 2025年の非課税枠はいくら?
2025年の制度では、以下のように非課税枠が定められています。
| 住宅の種類 | 非課税限度額(2025年) |
|---|---|
| 省エネ住宅(※1) | 最大1,000万円 |
| 一般住宅 | 最大500万円 |
※1:断熱性や耐震性など、一定の基準を満たす住宅が対象。
これは2024年と比較すると縮小傾向にあり、制度の利用は“今がラストチャンス”といえるかもしれません。
3. 非課税制度を利用するための条件
非課税制度を使うには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
贈与を受けた人の年齢が18歳以上(2025年1月1日時点)
-
贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下
-
贈与を受けた資金を住宅購入費に充てること
-
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、購入契約書のコピーなどを添付し、贈与税の申告を行うこと
4. 申告を忘れずに!非課税でも「贈与税の申告」は必須
ここでよくある誤解が「非課税なら申告不要」というもの。
実は非課税になる場合でも、税務署への申告は絶対に必要です。
以下の書類が必要になります。
-
贈与税の申告書
-
贈与契約書の写し
-
住宅の売買契約書や工事請負契約書
-
登記事項証明書など
申告をしなければ、たとえ非課税対象であっても、贈与税が課される可能性があります。
5. 親からの援助、いつ・いくらもらうべき?
贈与のタイミングによって、非課税制度の対象かどうかが変わります。住宅取得資金の贈与非課税は「契約日ベース」です。贈与を受ける年と契約する年がずれていると対象外になる可能性もあるので、スケジューリングが重要です。
また、親からの援助は「住宅購入代金のうちどこまで使うか」も考慮する必要があります。自己資金とバランスよく使うことで、ローン審査にもプラスに働きます。
6. よくある質問Q&A
Q1:贈与されたお金をリフォームに使っても非課税になりますか?
→ 一定の条件を満たす増改築であれば、非課税制度の対象になります。
Q2:兄弟姉妹も同じく贈与を受けて家を買う予定ですが、条件は共通ですか?
→ 非課税枠は「個人ごと」に設定されており、それぞれが要件を満たせば利用可能です。
Q3:現金をもらってから時間が経っている場合でも大丈夫?
→ 基本的には、贈与と住宅契約のタイミングが同一年内である必要があります。
7. 贈与を活用する前に、確認すべき3つのこと
-
贈与契約書の作成:口頭ではなく、文書で残しておくことがトラブル防止に。
-
税理士や専門家への相談:税制の理解には専門知識が必要。個別の相談をおすすめします。
-
住宅会社への事前確認:非課税制度の対象となる住宅か、建築会社に必ず確認しましょう。
8. 贈与での住宅購入における注意点
-
名義はどうするか?(共有名義の扱いは複雑です)
-
贈与額が非課税枠を超えた場合の対応
-
将来の相続との関係
これらはすべて、将来的なトラブルや税負担に直結します。早めに準備と確認をしておくことが大切です。
まとめ:非課税制度は活用してこそ意味がある
贈与を受けて住宅を購入するという選択は、人生の中でも大きな節目。
2025年の制度は使い方次第で、数百万円単位の節税が可能になります。
だからこそ、制度を正しく理解し、計画的に進めることが成功のカギです。
ご相談は「おうちの買い方相談室 高松店」へ!
「制度をもっと詳しく知りたい」
「我が家の場合どうなるの?」
「親との資金計画をどう組み立てれば?」
そんなお悩みは、住宅購入サポートのプロである私たちにお任せください!
人生に一度の大きな買い物、賢く進めましょう。