blog
家が建てられない土地とは?購入前に必ず知っておきたいチェックポイント
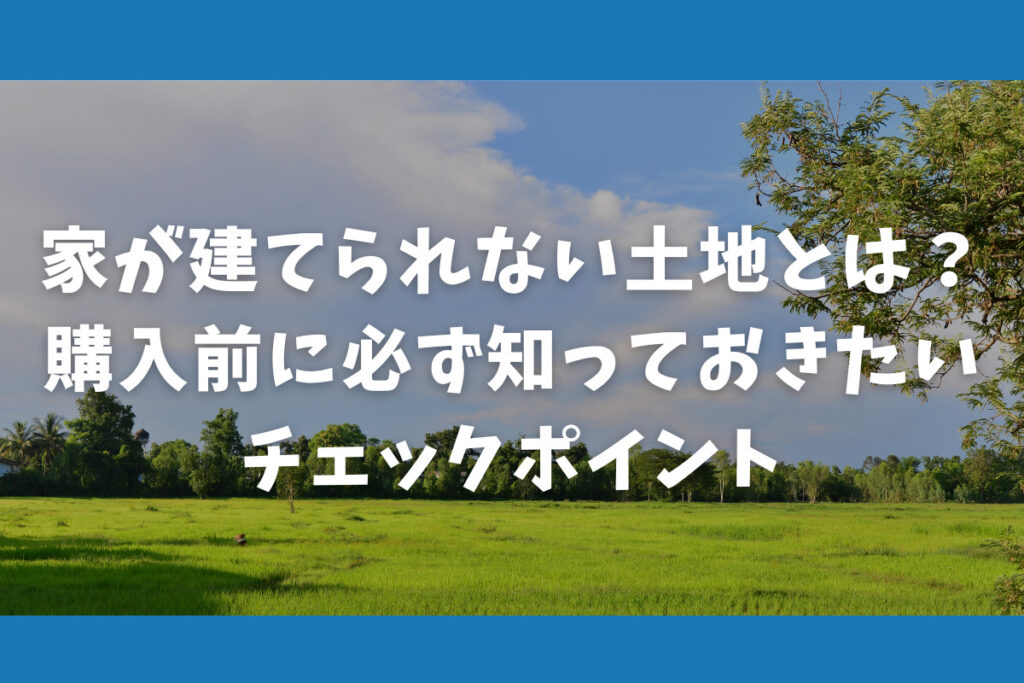
「そろそろマイホームを建てよう」と考えたとき、多くの方が最初に直面するのが「土地探し」です。
しかし、土地情報サイトや不動産広告を見て「価格が安い」「場所が良い」と思っても、その土地に家が建てられない場合があります。
建てられない土地を購入してしまうと、
-
建築確認が下りず家が建てられない
-
想定外の造成費が必要になる
-
売却しようにも買い手が見つからない
といった大きなトラブルに発展します。
この記事では、「建てられない土地」とはどんな土地なのかを法的・物理的・環境的・権利的な観点からすべて整理し、購入前に確認すべきチェックポイントを徹底解説します。
第1章 「建てられない土地」とは何か
土地があっても、すべての土地で家が建てられるわけではありません。
「建てられない土地」とは、建築基準法や都市計画法などの法令上の条件を満たさない土地、または物理的・権利的な理由で建築が困難な土地のことです。
理由は大きく分けて以下の6分類に整理できます。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| ① 法律上の制限 | 市街化調整区域・建築禁止区域など |
| ② 接道義務の未充足 | 建築基準法第43条違反(道路に2m以上接していない) |
| ③ 地盤・形状の問題 | 崖地・軟弱地盤・極端な高低差など |
| ④ 災害リスク区域 | 土砂災害・洪水・津波などの特別警戒区域 |
| ⑤ 権利・所有関係の問題 | 私道・共有地・登記不整合など |
| ⑥ インフラ・設備面 | 上下水道・電気・ガスなどの整備が不可能な土地 |
それぞれのパターンを詳しく見ていきましょう。
第2章 法律上「建てられない」土地
2-1 市街化調整区域
都市計画法で定められた「市街化調整区域」は、都市の無秩序な拡大を防ぐためのエリアです。
原則として、住宅や商業施設などの建築が禁止されています。
例外的に建てられるのは、
-
地元住民が自ら居住するための住宅(条件あり)
-
農業・林業など地域産業に必要な建築物
-
行政が許可を出した場合のみ
といった非常に限られたケースです。
【注意】
「市街化調整区域内なのに安い土地」が売られている場合は、ほとんどが建てられない土地です。
2-2 都市計画施設予定地
都市計画で将来的に道路、公園、河川などの公共施設の予定地となっている土地も、建築行為が制限されます。
建築確認を申請しても「都市計画法第53条」により不許可になる可能性があります。
2-3 農地(地目:田・畑)
「地目」が農地のままの土地は、原則として住宅を建てられません。
農地法の「農地転用許可」を得て、地目変更をしない限り建築行為は禁止されています。
特に、
-
農業振興地域
-
第1種農地
-
生産緑地地区
などに指定されている土地は、転用がほぼ不可能です。
2-4 防火地域・風致地区・景観地区
「建てられる」場合でも、建築制限が非常に厳しいエリアがあります。
防火地域では建物構造が制限され、風致地区や景観地区ではデザインや高さが制限されます。
制限により、
-
思い描いた家のデザインが建てられない
-
建築費が大幅に上がる
ことがあるため、結果的に“実質的に建てられない土地”になるケースもあります。
第3章 接道義務を満たさない土地
3-1 接道義務とは
建築基準法第43条では、建物を建てるための土地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないと定められています。
これを「接道義務」といいます。
この条件を満たさない土地は、建築確認が下りず、建てられない土地です。
3-2 「道路っぽいけど実は道路でない」ケース
・私道(所有者が個人)
・里道(りどう)や水路敷
・幅員が4m未満の古い道
これらは法的な「道路」とみなされず、接道義務を満たさないケースがあります。
たとえ「前面道路あり」と広告に書かれていても、法的道路でなければ建築不可です。
3-3 再建築不可物件
接道義務を満たしていない土地に建っている建物は、
「再建築不可物件」と呼ばれます。
一度取り壊すと新しい建物を建てることができず、将来的に売却や建て替えができないリスクがあります。
第4章 地盤・形状・高低差による制限
4-1 崖地・がけ条例区域
崖地に面した土地や、傾斜地では「がけ条例」により建築制限がかかります。
一定の高さの崖から一定距離を確保しなければ建築できません。
安全対策として擁壁工事が必要な場合もあり、工事費用が高額になるだけでなく、
物理的に建てられないケースも存在します。
4-2 軟弱地盤・液状化リスク地帯
地盤が弱い土地では、建物が沈下したり傾いたりする危険があるため、地盤改良工事が必須です。
ただし、地質によっては改良工事そのものが不可能な場合もあり、実質的に建築が困難となります。
4-3 極端に狭い・変形した土地
旗竿地(細長い形状)や三角形などの変形地では、
建築面積や間取りに制限が生じます。
とくに旗竿部分の幅が2m未満だと、接道義務を満たさず建築不可です。
第5章 災害リスクによる制限
5-1 土砂災害特別警戒区域
「レッドゾーン」と呼ばれる土砂災害特別警戒区域では、
構造上の安全性を確保できない場合、建築が禁止されます。
行政が指定する区域では、建築確認そのものが下りないことがあります。
5-2 洪水・浸水想定区域
洪水・津波の危険性が高いエリアでは、建築基準法上の構造制限がかかります。
基礎を高くしたり、避難経路を確保するなど追加工事が必要で、結果的に建てられないケースもあります。
5-3 地滑り・断層・火山活動地域
活断層や地滑り地帯、火山噴火の影響が想定される区域では、
建築そのものが禁止または制限されることがあります。
第6章 権利関係の問題による建築不可
6-1 私道・共有地のトラブル
前面道路が私道の場合、所有者の許可がないと通行・配管・建築ができません。
許可が得られない場合、家を建てることができません。
また、複数人で共有している土地(共有名義)では、
共有者全員の同意がなければ建築行為ができません。
6-2 地役権・通行権・賃借権の制限
他人の通行権や上下水道管の埋設権が設定されている土地では、
建築スペースが制限される場合があります。
登記簿を確認し、どんな権利が設定されているかを必ずチェックすることが重要です。
6-3 登記不整合・境界未確定
登記簿と実際の土地の境界が一致していない土地は、建築確認が出ないことがあります。
隣地との境界紛争が発生している場合も、建築はストップします。
第7章 インフラ・設備面による建築困難
7-1 上下水道が整備されていない
水道本管が近くにない土地では、引き込み工事が数百万円かかることもあります。
また、農業用水路しかないエリアでは、生活用水としての利用が難しく建築許可が出ない場合も。
7-2 電気・ガス・排水が通っていない
山間部や離島などでは電線やガス管が届いていないこともあります。
インフラ整備のために高額な工事費用が発生する場合、
「実質的に建てられない土地」となります。
第8章 その他の特殊ケース
-
文化財保護区域:発掘調査や工事制限あり
-
河川法区域・堤防保全区域:建築禁止
-
空港周辺・自衛隊基地周辺:高さ制限・防音制限あり
-
墓地・埋葬地跡地:法的・心理的要因で建築不可
第9章 建てられない土地を避けるための実践チェックリスト
| 確認項目 | チェック方法 |
|---|---|
| 市街化区域 or 調整区域 | 市役所 都市計画課 |
| 接道義務(4m幅・2m接道) | 建築士・不動産会社 |
| 地目(宅地以外か) | 登記簿確認 |
| ハザードマップ(災害区域) | 自治体HP |
| 私道・権利関係 | 法務局・不動産業者 |
| インフラ状況(上下水・電気・ガス) | 現地確認・役所窓口 |
第10章 トラブルを防ぐために専門家に相談を
土地の安全性や法的制限は、一般の方が見ただけでは判断できません。
見た目は「空き地」でも、法的には建てられない土地であることは珍しくないのです。
おうちの買い方相談室 高松店では、
・不動産
・建築会社
・住宅ローン
の各分野を総合的にチェックし、「その土地、本当に建てられるのか?」を専門家が無料で確認します。
まとめ
建てられない土地の理由は多岐にわたります。
法律・地盤・形状・権利・災害・インフラ…どれか一つでも問題があれば、家は建てられません。
「安い」「広い」といった条件に飛びつく前に、
“その土地が本当に家を建てられる土地か”を確認することが最優先です。
▶ 家づくりを安心して進めたい方へ
おうちの買い方相談室 高松店では、
土地選びから建築会社選び・住宅ローンまで、ワンストップでサポートしています。
「この土地、建てられるのかな?」と少しでも不安を感じたら、
ぜひ一度ご相談ください。
📞 無料相談予約はこちら → [お問い合わせフォーム]
🏠 おうちの買い方相談室 高松店

